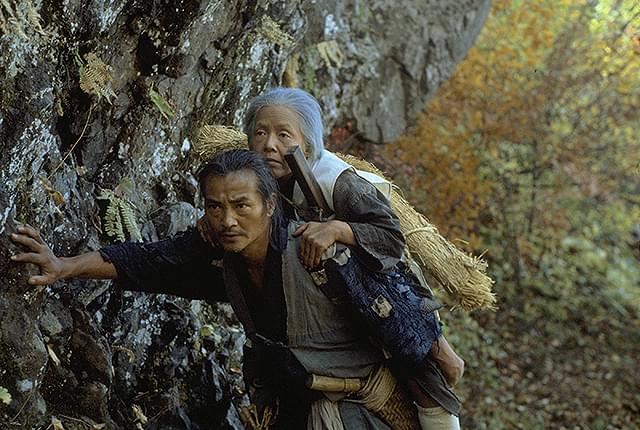TOP > 『哀れなるものたち』ネタバレあらすじと感想!フェミニズムと成長を描く唯一無二の傑作
『哀れなるものたち』ネタバレあらすじと感想!フェミニズムと成長を描く唯一無二の傑作

映画『哀れなるものたち』とは?まず知っておきたい基本情報
『哀れなるものたち』は、ギリシャ出身の鬼才ヨルゴス・ランティモス監督が手がけた2023年公開の映画です。
原題は「Poor Things」で、スコットランドの作家アラスター・グレイが1992年に発表した同名ゴシック小説を映画化した作品なんですよ。
監督のヨルゴス・ランティモスといえば、『女王陛下のお気に入り』や『聖なる鹿殺し』などで知られる独創的な作風の持ち主です。
そして本作で主人公ベラを演じるのは、『ラ・ラ・ランド』で有名なエマ・ストーンです。
エマ・ストーンは『女王陛下のお気に入り』に続き、ランティモス監督と再びタッグを組んでいます。
共演陣も豪華で、ウィレム・デフォー、マーク・ラファロ、ラミー・ユセフといった実力派俳優が脇を固めていますよ。
本作は第80回ヴェネチア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を受賞し、第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演女優賞など11部門にノミネートされました。
そして見事にエマ・ストーンが主演女優賞を獲得したほか、美術賞、衣装デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞の4部門で受賞しています。
上映時間は142分で、日本ではR18+指定となっていますので、18歳未満の方は鑑賞できない作品です。
この指定は作品に含まれる性的描写や暴力表現によるものですが、これらは物語のテーマと深く結びついているんですね。
『哀れなるものたち』のあらすじを徹底解説【ネタバレ注意】
ここからは映画『哀れなるものたち』のあらすじを詳しく解説していきます。
ネタバレを含みますので、まだ映画を観ていない方はご注意くださいね。
ベラの誕生と奇妙な屋敷での生活
物語の舞台は19世紀のロンドンです。
天才外科医のゴドウィン・バクスター(通称”ゴッド”)の屋敷には、ベラ・バクスターという若い女性が暮らしていました。
しかしベラの言動は非常に奇妙で、大人の体を持ちながら、まるで幼児のような振る舞いをするんです。
ピアノを足で叩いたり、高価な皿を次々と割ったり、突然癇癪を起こしたりと、その行動は予測不可能でした。
実はベラには驚くべき秘密がありました。
ゴドウィンの助手となった医学生マックス・マッキャンドレスに、ゴッドは真実を明かします。
ベラはもともと妊娠していた女性が橋から飛び降り自殺を図った際、ゴドウィンが遺体を回収し、その女性の脳を身籠っていた胎児の脳と入れ替えて蘇生させた存在だったのです。
つまりベラは大人の肉体に赤ん坊の脳を持つという、科学実験の産物だったんですね。
この設定は明らかにメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を想起させます。
ゴドウィンは自らの父親から人体実験の対象とされた過去を持ち、その身体には数々の手術痕が残っています。
そんな彼が創造したベラは、まさに「怪物に作られた怪物」と言えるでしょう。
ベラは急速に成長し、知識や経験を貪欲に吸収していきます。
外の世界への好奇心が抑えられなくなったベラに、ゴドウィンはマックスと結婚させることを考えました。
しかし運命はそう単純には進みません。
放蕩弁護士ダンカンとの大陸横断の旅
そこへ放蕩癖のある弁護士ダンカン・ウェダバーンが現れます。
ダンカンはベラをゴドウィンの屋敷から連れ出し、大陸横断の旅に誘いました。
外の世界への憧れを抑えられなかったベラは、この誘いに乗ってしまいます。
リスボンでの滞在中、ベラとダンカンは性的な関係を持ちます。
ベラにとって初めての性体験は、新たな発見と快楽の世界への扉でした。
しかし純粋な好奇心からセックスを楽しむベラに対し、ダンカンは次第に独占欲と嫉妬心に苦しめられるようになります。
ベラを自分の手元に置いておきたいダンカンは、彼女を騙して豪華客船に乗せました。
船の中なら外に出られないと考えたのです。
しかし船上でベラは老婦人マーサや黒人青年ハリーと出会い、読書を通じて知識を深めていきます。
彼らとの交流を通じて、ベラは世界の残酷さや不平等を知ることになるんです。
アレクサンドリアで停泊した際、ハリーはベラを貧民窟を見下ろせる場所へ連れて行きました。
そこでは子供たちが飢えて死に、多くの人々が虐げられている現実がありました。
この経験はベラに大きな衝撃を与え、恵まれた自分と困窮する人々との格差を認識させます。
ショックを受けたベラは、ダンカンがカジノで大勝して散らかした札束を集め、困っている人々に渡そうとしますが、船員に騙されてしまいます。
こうして一文無しになった二人はパリで船を降ろされることになりました。
パリの娼館での経験と驚くべき成長
金銭的に困窮したベラは、パリの娼館で働くことを決断します。
ダンカンは激怒しますが、ベラの意志は固く、彼女は独立した道を選んだのです。
娼館での生活は、ベラにとって新たな学びの場となりました。
セックスワーカーとして働く中で、ベラは自分の身体は自分のものだという認識を深めていきます。
単なる性的搾取の場としてではなく、本作は娼館での経験をベラの主体性獲得の過程として描いているんですね。
ベラは客との会話を楽しみ、ユーモアで場を和ませ、自分のメンタルと身体を守る術を身につけていきました。
この時期、ベラは医学を学ぶ決心もします。
かつて自分を創造したゴドウィンのような医師になりたいと考えたのです。
過去との対峙と衝撃のラスト
そんな中、ベラの前に突然現れたのがアルフィー・ブレシントン将軍でした。
彼はベラの元夫だと名乗り、彼女を屋敷に連れ戻そうとします。
ゴドウィンの屋敷に戻ったベラは、自分の過去を知ることになりました。
かつてベラはヴィクトリアという名の女性で、アルフィーという支配的でサディスティックな夫に虐げられていたのです。
暴力と抑圧に耐えかね、妊娠していたヴィクトリアは橋から身を投げて自殺を図りました。
アルフィーはベラを再び自分の支配下に置こうとし、性的快楽を奪うためにクリトリスを切除しようとまでします。
しかしもはやベラは、かつてのヴィクトリアではありません。
彼女はアルフィーの足を銃で撃ち抜き、最終的にはゴドウィンがかつて自分にしたように、アルフィーの脳をヤギの脳と入れ替えてしまうのです。
こうしてベラは過去の抑圧者に決着をつけ、完全な自立を果たしました。
映画は、ゴドウィンが亡くなった後、医師としての道を歩み始めたベラが、屋敷で仲間たちと穏やかに暮らす姿で幕を閉じます。
『哀れなるものたち』を観た感想|唯一無二の映像体験
ここからは実際に映画を観た感想をお伝えしていきます。
圧倒的な独創性を持つ世界観と映像美
まず何よりも印象的なのは、この映画の唯一無二の世界観です。
19世紀のロンドンを舞台にしながらも、現実とは明らかに異なる異世界のような雰囲気が漂っているんですよ。
魚眼レンズを多用した歪んだ映像、モノクロとカラーを行き来する演出、そして円形のモチーフが繰り返し登場する構図など、視覚的な工夫が随所に凝らされています。
建物や衣装、乗り物のデザインも極めて独創的で、どこか見たことがあるようでいて、決して現実には存在しない「おとぎ話のような世界」が広がっています。
この独特の美術と衣装デザインが、アカデミー賞を受賞したのも納得の完成度ですよ。
空の色さえも現実離れしていて、まるで絵画の中に入り込んだような感覚になります。
こうした寓話的な世界設定だからこそ、物語に含まれる社会批評やメッセージがより際立って見えてくるんですね。
エマ・ストーンの圧倒的な演技力に脱帽
本作で何といっても素晴らしいのは、エマ・ストーンの演技です。
冒頭では本当に幼児のような拙い動きと話し方をしていたベラが、物語が進むにつれて知性と主体性を獲得していく過程を、エマ・ストーンは見事に演じ分けています。
ノーメイクに近い状態で、R18指定になるほどの大胆な性描写にも臆することなく挑んだその姿勢には、女優としての覚悟が感じられますよ。
特に印象的なのは、ダンカンと踊るダンスシーンです。
ダンカンが必死に型通りのダンスに導こうとするのに対し、ベラは決して従わず、自分独自の動きを貫き通します。
この場面は、男性の支配に屈しない女性の主体性の獲得を象徴的に表現していて、本作のテーマが凝縮されているシーンだと感じました。
アカデミー賞主演女優賞を獲得したのも当然と言える、圧巻のパフォーマンスでした。
女性の自立と成長を描くフェミニズム的視点
『哀れなるものたち』は、明確にフェミニズム的なメッセージを持った作品です。
ただし、それは説教臭いものではなく、ベラという一人の女性の成長物語として描かれているんですね。
ベラは「男に作られた女」として誕生しますが、やがて男性たちの都合のいい存在であることを拒否し、自分自身のアイデンティティを確立していきます。
ゴドウィンは保護者として、マックスは恋人として、ダンカンは所有者として、アルフィーは支配者として、それぞれベラを自分の手元に置こうとしますが、ベラは誰の所有物にもならないんです。
特に興味深いのは、娼館での経験がネガティブに描かれていない点です。
セックスワーカーとして働くことを通じて、ベラは「私の身体は私のものだ」という認識を深めていきます。
性的な経験が女性の成長と主体性獲得につながるという描き方は、従来の映画では見られなかった視点ですよね。
最終的にベラは医師になることを選び、かつて自分を支配しようとした男性を逆に手術台に乗せるという展開は、完全な立場の逆転を象徴しています。
性描写の意味と必然性について
本作がR18指定を受けた理由は、作中に登場する数多くの性描写です。
確かに露骨なシーンも多く、人によっては不快に感じる可能性もあるでしょう。
しかしこれらの性描写は決して興味本位や刺激目的ではなく、物語のテーマと深く結びついているんですよ。
ベラにとってセックスは、最初は単なる好奇心の対象であり、新たな発見でした。
しかし旅を通じて、それが男性による支配や搾取の道具として使われることも知ります。
同時に、自分の身体と性は自分でコントロールできるものだという認識も深めていくんです。
ヨルゴス・ランティモス監督特有の「無味乾燥なセックス」の描写は、セクシーさを排除することで、かえって性行為の持つ権力関係や社会的意味を浮き彫りにしています。
またベラが娼館で女性客と関係を持つシーンや、ラストで女性パートナーと暮らしているシーンからは、ベラの性のあり方が極めて自由で多様であることが示されています。
これらの描写があるからこそ、本作のフェミニズム的メッセージがより説得力を持つんですね。
『哀れなるものたち』のテーマを深く考察
フランケンシュタインとの共通点
本作は明らかにメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』をモチーフにしています。
科学者が死体を蘇生させるという設定だけでなく、「創造者と被造物」という関係性も共通していますよね。
興味深いのは、原作『フランケンシュタイン』の作者メアリー・シェリー自身が、フェミニズム思想家の娘であるという点です。
『哀れなるものたち』も同様に、女性の主体性や自立というフェミニズム的テーマを扱っているんです。
ただし『フランケンシュタイン』の怪物が社会から拒絶され悲劇的な結末を迎えるのに対し、ベラは社会との関わりの中で成長し、自分の居場所を見つけます。
この違いこそが、本作の現代的なメッセージなのかもしれませんね。
身体と精神のアイデンティティ
本作が提示する興味深いテーマの一つが、身体と精神の関係性です。
ベラは母親の身体に胎児の脳を持つという、身体と精神が一致していない存在として誕生しました。
そして成長するにつれ、自分が何者であるかを精神面から構築していくんですね。
周囲の人々は彼女の外見に惹かれ、身体を所有しようとしますが、ベラのアイデンティティは精神にあります。
「私が何者かは私の心が決める」というメッセージは、現代のジェンダーやセクシュアリティの議論とも重なる部分があると感じました。
トランスジェンダーのナラティブとも通じる要素を持っているとも解釈できますよね。
哀れなのは誰なのか
タイトルの「哀れなるものたち」とは、一体誰を指しているのでしょうか。
一つの解釈は、ベラを所有しようとして振り回される男性たちです。
ダンカンは嫉妬に狂い、アルフィーは最後にヤギになってしまいます。
彼らは女性を支配できると思い込んでいたのに、結局は自分たちが滑稽な存在になってしまうんですね。
もう一つの解釈は、社会の偏見や常識に縛られている人々全般を指しているとも考えられます。
ベラのように自由で偏見のない視点を持てない人々こそが「哀れ」なのかもしれません。
そしてもう一つ、ラストでベラ自身がマッドサイエンティストとしての資質を持ってしまったという点も見逃せません。
特殊な力を持った者への警告という意味も込められているのでしょう。
どこで観られる?『哀れなるものたち』の配信情報
『哀れなるものたち』を観たいと思ったあなたに、視聴方法をお伝えしますね。
本作は現在、Disney+(ディズニープラス)で見放題配信されています。
Disney+は月額990円(税込)から利用でき、本作以外にもヨルゴス・ランティモス監督の『女王陛下のお気に入り』や『憐れみの3章』も視聴できますよ。
また、Amazon Prime VideoやHuluでもレンタル・購入が可能です。
ブルーレイ+DVDセットも発売されていますので、何度も観たい方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。
ただしR18+指定の作品ですので、18歳未満の方は視聴できませんのでご注意くださいね。
こんな人に『哀れなるものたち』をおすすめしたい
最後に、どんな人にこの映画をおすすめしたいかをお伝えします。
まず、ヨルゴス・ランティモス監督の過去作品が好きな方には間違いなくおすすめです。
『女王陛下のお気に入り』や『ロブスター』の独特な世界観が好きだった方なら、本作もきっと楽しめるでしょう。
また、エマ・ストーンのファンの方にもぜひ観ていただきたいですね。
彼女のキャリアの中でも屈指の演技が見られますよ。
アート系の映画や独創的な映像美を堪能したい方にもぴったりです。
フェミニズムやジェンダーの問題に関心がある方なら、本作が提示するメッセージに共鳴できるはずです。
ただし、性描写やグロテスクな表現が苦手な方にはおすすめできません。
また、わかりやすいエンターテインメントを求めている方には向かないかもしれませんね。
本作は確かに癖が強く、万人受けする映画ではありません。
しかし、映画の持つ可能性や表現の幅を感じたい方、一度見たら忘れられない強烈な体験を求めている方には、ぜひ観ていただきたい作品です。
『哀れなるものたち』は、あなたの映画体験を確実に更新してくれる一本になるはずですよ。
キーワード
おすすめ記事
-
2025.11.10
落下の解剖学あらすじ・感想を徹底解説!パルムドール受賞作の結末と真相考察
-
2025.11.18
『時をかける少女』あらすじ完全ガイド!感動の結末と千昭の真実を徹底解説
-
2025.09.30
ABEMAプレミアムの口コミ評判まとめ!利用者が語る本音のメリット・デメリット完全ガイド
-
2025.12.22
スクリームのあらすじと感想を徹底解説!犯人の正体と動機、見どころをネタバレありで紹介