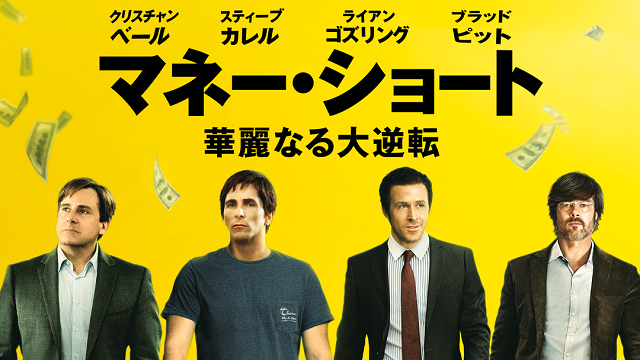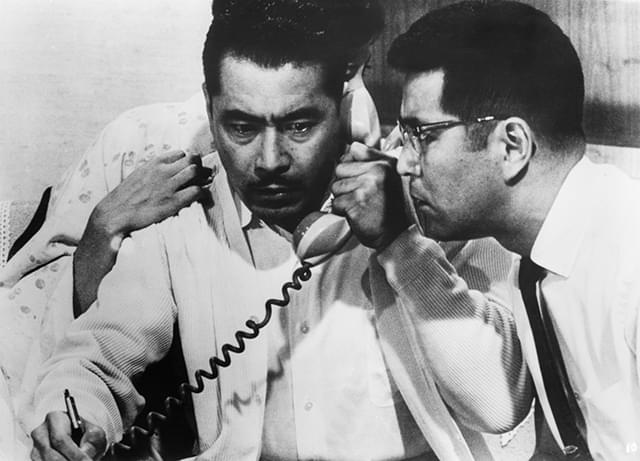TOP > 子どもの視聴時間制限設定ガイド!デバイス別・VOD別に徹底解説
子どもの視聴時間制限設定ガイド!デバイス別・VOD別に徹底解説

子どもの動画視聴時間、制限は必要?保護者が知るべき理由
YouTubeやNetflix、Disney+などの動画配信サービスが身近になった今、お子さんが毎日何時間も動画を見続けて困っているという保護者の声が増えています。
「気づいたら何時間も見ている」「夜遅くまで動画を見て朝起きられない」「宿題や勉強がおろそかになっている」など、お子さんの動画視聴に関する悩みは尽きません。
動画コンテンツは面白く、次から次へとおすすめ動画が表示されるため、子どもが自分で視聴をやめることは非常に難しいのです。
長時間の動画視聴は、睡眠不足や生活リズムの乱れ、学習時間の減少、さらには視力低下や姿勢の悪化など、お子さんの健康や成長にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
また、スマホ依存やネット依存の入り口になることもあり、早い段階から適切な管理が必要です。
だからこそ、保護者の方が視聴時間を適切に制限し、お子さんが健全にデジタルコンテンツを楽しめる環境を整えることが大切なんですよ。
この記事では、スマートフォンやタブレット、テレビなど各デバイスでの視聴時間制限設定方法を、具体的に分かりやすく解説していきます。
年齢別:子どもに適切な1日の視聴時間の目安
視聴時間の制限を設定する前に、まずはお子さんの年齢に応じた適切な視聴時間の目安を知っておきましょう。
小児科学会や教育専門家の推奨を参考にすると、以下のような目安が示されています。
0歳〜2歳
この年齢では、できるだけスクリーンタイムは避けることが推奨されています。
脳の発達が著しい時期であり、画面を見るよりも実際の体験や人との触れ合いが重要です。
どうしても必要な場合でも、保護者と一緒に短時間(15分程度)にとどめましょう。
3歳〜5歳(未就学児)
1日1時間以内が目安です。
この時期は、外遊びや絵本の読み聞かせ、創造的な遊びなど、動画視聴以外の活動とバランスを取ることが大切ですよ。
視聴する場合は、保護者が一緒に見て内容を確認し、お子さんとコミュニケーションを取りながら楽しむことをおすすめします。
6歳〜12歳(小学生)
1日2時間以内が推奨されています。
ただし、宿題や習い事、外遊びなどの時間を確保した上で、残った時間内で視聴することが前提です。
学年が上がるにつれて学習量も増えるため、平日と週末で時間を分けて設定するのも効果的でしょう。
13歳以上(中学生・高校生)
中学生の平均的なスマホ利用時間は1日2〜3時間というデータがありますが、これには動画視聴以外のSNSやゲームも含まれます。
部活動や勉強との両立を考えると、動画視聴は1日1〜2時間程度に抑えるのが理想的です。
この年齢になると自己管理能力も育ってきますので、お子さんと話し合ってルールを決めることが大切ですよ。
これらの目安を参考にしながら、お子さんの生活リズムや家庭の状況に合わせて、適切な視聴時間を設定していきましょう。
スマートフォン・タブレットでの時間制限設定方法
お子さんがスマートフォンやタブレットで動画を視聴する場合、デバイスの設定機能やアプリを活用することで、効果的に時間制限をかけることができます。
ここでは、iPhone(iPad)とAndroidそれぞれの設定方法を詳しく解説します。
iPhoneでスクリーンタイムを使う方法
iPhoneやiPadには「スクリーンタイム」という標準機能が搭載されており、アプリごとの使用時間を制限できます。
お子さんのiPhoneに時間制限を設定する場合、この機能を使うのが最も簡単で効果的です。
スクリーンタイムの設定手順
まず、iPhoneの「設定」アプリを開き、「スクリーンタイム」をタップします。
次に「App使用時間の制限」を選択し、「制限を追加」をタップしてください。
制限したいアプリのカテゴリ(エンターテインメントなど)を選択するか、個別にYouTubeやNetflixなどのアプリを指定します。
1日の使用時間を設定し、曜日ごとに異なる時間を設定することも可能ですよ。
設定した時間を超えると、アプリのアイコンがグレーになり起動できなくなります。
スクリーンタイム・パスコードの設定
お子さんが自分で制限を解除できないよう、必ず「スクリーンタイム・パスコード」を設定しましょう。
「スクリーンタイム」の画面から「スクリーンタイム・パスコードを使用」を選択し、保護者だけが知っている4桁の数字を設定してください。
これにより、制限時間の延長やスクリーンタイムの設定変更には、必ずパスコードの入力が必要になります。
Androidでファミリーリンクを使う方法
Androidスマートフォンやタブレットでは、Googleが提供する「ファミリーリンク」というアプリを使うことで、お子さんのデバイスを管理できます。
ファミリーリンクは、視聴時間の制限だけでなく、アプリの使用状況確認や位置情報の把握なども可能な総合的な見守りツールです。
ファミリーリンクの設定手順
まず、保護者のスマートフォンに「Google ファミリーリンク(保護者向け)」アプリをダウンロードします。
次に、お子さんのスマートフォンに「Google ファミリーリンク(お子様向け)」アプリをダウンロードしてください。
保護者のアプリから「お子様を追加」を選択し、画面の指示に従って設定を進めます。
お子さんのGoogleアカウントと保護者のアカウントをリンクさせることで、管理が開始されます。
利用時間の上限設定
ファミリーリンクアプリを開き、お子さんを選択します。
「利用時間の制限」をタップし、「1日の利用時間の上限」をオンにしてください。
曜日ごとに異なる時間を設定できるため、平日は短く、週末は少し長めにするなど、柔軟な設定が可能です。
また、「おやすみ時間」を設定すれば、就寝時刻になると自動的にデバイスがロックされますよ。
YouTube Kidsのタイマー設定
小さなお子さん向けには、YouTube Kidsアプリの利用がおすすめです。
YouTube Kidsには、子ども向けコンテンツのみが表示され、なおかつアプリ内にタイマー機能が搭載されています。
タイマーの設定方法
YouTube Kidsアプリを起動し、画面右下の南京錠アイコンをタップします。
表示された計算式を解くか、設定したパスコードを入力してください。
タイマーアイコンを選択し、1分〜60分の範囲で制限時間を設定します。
「タイマーを開始」をタップすると、設定した時間が経過すると「時間だよ、またね!」という通知が表示され、アプリが自動的にロックされます。
ただし、お子さんが成長してYouTube Kidsから通常のYouTubeアプリに切り替えられるようになると、この制限は効かなくなります。
そのため、デバイス全体の時間制限と組み合わせることが重要ですよ。
テレビでの視聴時間制限設定(デバイス別)
お子さんがテレビで動画配信サービスを視聴している場合、テレビやストリーミングデバイスの設定で時間制限をかけることができます。
ただし、デバイスによって対応している機能が異なるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
Google TV搭載テレビでの設定
テレビでの視聴時間制限において、最も実用的で強力な機能を持つのがGoogle TVです。
Google TVが搭載されたシャープのAQUOSやソニーのブラビアなどの最新モデルでは、子ども専用プロフィールを作成し、細かく視聴時間を管理できます。
子ども用プロフィールの作成
Google TVのホーム画面から「設定」に移動し、「アカウントとプロフィール」を選択します。
「プロフィールを追加」から子ども用プロフィールを作成してください。
生年月日を入力すると、年齢に応じた適切な制限が自動的に設定されます。
1日の利用時間制限
子ども用プロフィールの設定画面で、1日の利用時間の上限を15分単位で設定できます。
曜日ごとに異なる時間を設定できるため、平日は1時間、週末は2時間といった柔軟な管理が可能ですよ。
設定した時間に達すると「タイムアウト」画面が表示され、保護者の暗証番号またはパスワードを入力しないと視聴を再開できません。
おやすみ時間の設定
就寝時刻や勉強時間など、視聴できない時間帯を「おやすみ時間」として設定できます。
この時間帯になると、子ども用プロフィールからは自動的にロックがかかり、視聴ができなくなります。
ファミリーリンクとの連携
Google TVはファミリーリンクアプリと連携させることで、保護者のスマートフォンから遠隔操作で管理することも可能です。
外出先からでもお子さんの視聴状況を確認したり、必要に応じて制限をかけたりできるため、より安心ですよ。
Fire TV Stickでの対策
Amazon Fire TV Stickは、残念ながら視聴時間を自動的に制限する機能が標準では搭載されていません。
ただし、いくつかの対策方法があります。
機能制限(ペアレンタルコントロール)の設定
Fire TV Stickには「機能制限」という機能があり、年齢制限のあるコンテンツを視聴できないようにすることはできます。
Fire TVのホーム画面から「設定」→「環境設定」→「機能制限」と進み、PINコードを設定してください。
ただし、これはコンテンツの制限であり、時間制限ではない点に注意が必要です。
物理的な時間制限の方法
Fire TV Stickで時間制限を実現するには、外部デバイスを活用する方法があります。
SwitchBotプラグミニなどのスマートプラグをテレビのコンセントに接続し、スマートフォンアプリから電源のオン・オフをスケジュール設定できます。
設定した時間になると自動的にテレビの電源が切れるため、物理的に視聴を制限できますよ。
また、Wi-Fiルーターに「キッズタイマー」機能がある場合、特定の時間帯にFire TV StickのWi-Fi接続を遮断する方法も効果的です。
その他スマートTVでの制限方法
東芝のREGZAなど、他のメーカーのスマートテレビにも一定の制限機能が搭載されている場合があります。
REGZAの保護者による制限
REGZAでは、インターネットサービス全体へのアクセスを制限したり、動画アプリごとに暗証番号を設定したりできます。
YouTubeアプリを起動する際に暗証番号が必要になるよう設定することで、保護者の許可なく視聴できないようにすることが可能です。
ただし、時間で自動的に制限がかかる機能はないため、保護者が在宅時のみ許可するといった運用になります。
YouTube Kidsアプリの利用
スマートテレビでYouTube Kidsアプリが利用できる場合、スマートフォン版と同様にタイマー機能を使うことができます。
ただし、通常のYouTubeアプリや他の動画配信サービスアプリは制限できないため、他のアプリを削除するか、起動できないように設定する必要があります。
テレビでの視聴時間制限を確実に行いたい場合は、Google TV搭載テレビの導入、またはGoogle TV with Chromecastを既存のテレビに接続する方法が最も効果的ですよ。
主要VODサービス別:ペアレンタルコントロール機能
動画配信サービス(VOD)各社も、子どもが安全に視聴できるよう、さまざまなペアレンタルコントロール機能を提供しています。
ここでは主要サービスごとの機能と設定方法をご紹介します。
Netflix
Netflixは子ども向けコンテンツが充実しており、プロフィール機能とペアレンタルコントロールも充実しています。
キッズプロフィールの作成
Netflixでは、アカウント内に複数のプロフィールを作成でき、その中にキッズ専用プロフィールを設定できます。
プロフィール作成時に「キッズですか?」という質問に「はい」と答えると、12歳以下向けのコンテンツのみが表示されるようになります。
キッズプロフィールでは、暴力的な表現や不適切な内容が含まれる作品は自動的に除外されますよ。
視聴制限レベルの設定
アカウント設定から「プロフィールとペアレンタルコントロール」を選択し、お子さんのプロフィールを選んでください。
「視聴制限」の項目で、「未就学児」「小学生向け」「ティーン向け」など、年齢に応じたレベルを選択できます。
PINコードを設定すれば、制限レベル以上の作品を視聴する際にPINの入力が必要になります。
時間制限について
Netflixアプリ自体には視聴時間を制限する機能はありませんが、前述のスマートフォンやテレビのデバイス設定と組み合わせることで管理できます。
Disney+(ディズニープラス)
Disney+はディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズなど、家族で楽しめるコンテンツが豊富な動画配信サービスです。
キッズプロフィール機能
Disney+でもプロフィールごとに視聴制限を設定できます。
プロフィール作成時に「キッズプロフィール」を選択すると、ディズニージュニアやピクサーなど、子ども向けコンテンツのみが表示されます。
年齢制限も細かく設定でき、G(全年齢対象)やPG(保護者の助言が必要)など、段階的な制限が可能ですよ。
PINコードによる保護
プロフィール設定でPINコードを設定すると、大人向けプロフィールへの切り替えにPINが必要になります。
これにより、お子さんが勝手に大人向けコンテンツを視聴することを防げます。
あんしんモード(一部対応)
一部のDisney+対応デバイスでは、視聴時間を制限する機能が提供されていますが、すべてのデバイスで利用できるわけではありません。
基本的にはデバイス側の時間制限機能と組み合わせて利用することをおすすめします。
Hulu
Huluは日本のテレビ番組やアニメが充実しており、子ども向けコンテンツも豊富です。
Huluキッズの利用
Huluには「Huluキッズ」という子ども向けの専用ページがあります。
プロフィール作成時に「お子様」を選択すると、キッズ向けコンテンツのみが表示される仕様になっています。
アンパンマンやしまじろう、ポケモンなど、人気のキッズ番組が多数揃っていますよ。
あんしんモード
Huluキッズの大きな特徴が「あんしんモード」です。
この機能を有効にすると、視聴時間の制限を設定でき、設定した時間に達すると自動的に視聴が停止されます。
さらに、残り時間が画面上に表示され、色も変化するため、お子さん自身が視覚的に残り時間を認識できる工夫がされています。
暗証番号設定
大人向けプロフィールへの切り替えやあんしんモードの解除には、暗証番号の入力が必要です。
保護者だけが知っている番号を設定することで、お子さんが勝手に設定を変更することを防げます。
Amazonプライム・ビデオ
Amazonプライム会員なら追加料金なしで利用できるプライム・ビデオにも、子ども向けの機能があります。
Amazon Kids+の活用
Amazon Kids+(旧FreeTime Unlimited)は、子ども向けの有料サービスですが、年齢に応じたコンテンツフィルタリングと視聴時間制限が可能です。
ペアレントダッシュボードから、1日の利用時間制限やおやすみ時間を設定でき、細かく管理できますよ。
機能制限設定
通常のプライム・ビデオでも、アカウント設定から「機能制限」を有効にできます。
視聴制限レベルを設定し、PINコードを登録することで、年齢制限のある作品の視聴を防げます。
ただし、時間制限機能は標準では搭載されていないため、デバイス側の設定と併用する必要があります。
U-NEXT
U-NEXTは見放題作品数が国内最大級で、映画やドラマ、アニメまで幅広いジャンルが楽しめます。
ペアレンタルロック機能
U-NEXTでは、R指定作品やアダルトコンテンツを非表示にする「ペアレンタルロック」機能があります。
アカウント設定からセキュリティコードを設定し、ペアレンタルロックを有効にすることで、不適切なコンテンツからお子さんを守れます。
子アカウントの作成
U-NEXTは1つの契約で最大4つのアカウントを作成でき、子ども用のアカウントを別途設定できます。
子アカウントには購入制限をかけることができ、勝手にレンタル作品を購入することを防げますよ。
時間制限について
U-NEXTアプリ自体には視聴時間制限機能はありませんが、スマートフォンのスクリーンタイムやファミリーリンクと組み合わせることで管理可能です。
各VODサービスのペアレンタルコントロール機能を活用しつつ、デバイス側の時間制限設定と組み合わせることで、お子さんの視聴環境をより安全に整えられますよ。
視聴時間制限を成功させる親子ルール作りのコツ
技術的な設定も大切ですが、それ以上に重要なのが、お子さんと一緒にルールを作り、守る習慣をつけることです。
ここでは、視聴時間制限を成功させるための親子ルール作りのコツをご紹介します。
お子さんと話し合ってルールを決める
一方的に制限をかけるのではなく、なぜ視聴時間を制限する必要があるのかをお子さんに説明し、一緒にルールを考えましょう。
「1日○時間まで」「宿題が終わってから」「夜○時以降は見ない」など、具体的なルールを話し合って決めることで、お子さん自身が納得して守りやすくなります。
年齢に応じて、お子さんの意見も取り入れながら決めることが大切ですよ。
ルールは紙に書いて見える場所に貼る
決めたルールは紙に書いて、リビングなど家族みんなが見える場所に貼っておきましょう。
口約束だけでは忘れてしまいがちですが、文字にして可視化することで、お子さんも保護者も常に意識できます。
カラフルなペンで書いたり、イラストを添えたりすると、お子さんも楽しく確認できますよ。
ご褒美よりも自然な制限を
「宿題をしたら見てもいい」というルールは良いのですが、「テストで良い点を取ったら時間を延長」などのご褒美制にするのは避けましょう。
動画視聴がご褒美になってしまうと、過度に価値を感じてしまい、依存につながる可能性があります。
あくまで日常生活の一部として、自然に楽しめる範囲でルールを設定することが大切です。
保護者も一緒にルールを守る
お子さんにだけルールを押し付けるのではなく、保護者も一緒にスマホやテレビの時間を意識しましょう。
「夕食時はスマホを見ない」「寝る前1時間は家族全員がデジタルデバイスから離れる」など、家族共通のルールにすることで、お子さんも納得しやすくなります。
保護者が率先してルールを守る姿勢を見せることが、何よりも効果的な教育になりますよ。
定期的にルールを見直す
お子さんの成長や生活環境の変化に合わせて、定期的にルールを見直しましょう。
「前のルールが守れているか」「今のルールで困っていることはないか」など、お子さんと話し合う機会を持つことが大切です。
柔軟にルールを調整することで、お子さんも前向きにルールを守る姿勢が育ちます。
視聴時間以外の楽しみを増やす
動画視聴の時間を制限するだけでなく、他の楽しい活動を増やすことも重要です。
外遊びやスポーツ、読書、家族でのボードゲームなど、動画以外にも楽しいことがあることをお子さんに体験させましょう。
多様な楽しみ方を知ることで、動画への依存を自然に減らすことができますよ。
約束を破った時の対応を決めておく
ルールを破ってしまった時の対応も、あらかじめお子さんと話し合って決めておきましょう。
「翌日は視聴時間を半分にする」「1日視聴禁止」など、一貫性のある対応をすることで、お子さんもルールの重要性を理解します。
ただし、厳しすぎる罰則は逆効果になることもあるため、お子さんの年齢や性格に合わせて調整してくださいね。
親子で協力してルールを守る習慣ができれば、技術的な制限設定だけに頼らず、お子さん自身が健全なデジタルライフを送れるようになります。
よくある質問(FAQ)
子どもが視聴時間制限を勝手に解除してしまいます。どうすればいいですか?
スクリーンタイムやファミリーリンクの設定には、必ず保護者専用のパスコードやPINコードを設定しましょう。
お子さんに推測されにくい数字を選び、絶対に教えないことが重要です。
また、iPhoneの「設定」アプリそのものにもパスコードをかけることで、設定画面にアクセスできないようにする方法もあります。
それでも解除してしまう場合は、お子さんとしっかり話し合い、なぜルールを守る必要があるのかを理解してもらうことが根本的な解決につながりますよ。
複数のデバイスを持っている場合、すべてに設定が必要ですか?
はい、基本的にはお子さんが使用するすべてのデバイスに時間制限を設定する必要があります。
スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビなど、動画を視聴できるデバイスごとに制限をかけましょう。
Googleファミリーリンクやスクリーンタイムのファミリー共有機能を使えば、複数のデバイスを一元管理できるため、設定の手間を減らせます。
YouTubeだけ制限して、他のアプリは自由に使わせたいのですが?
iPhoneのスクリーンタイムやAndroidのファミリーリンクでは、アプリごとに個別に時間制限を設定できます。
YouTubeアプリだけを選択して1日30分などと設定すれば、他のアプリは制限なく使用できますよ。
ただし、SafariやChromeなどのブラウザからYouTubeにアクセスされる可能性もあるため、ブラウザも含めて制限することをおすすめします。
制限時間になったら通知だけで強制終了しない設定はできますか?
YouTubeアプリ内の「休憩のリマインダー」機能は、通知のみで強制終了はしません。
あくまでお子さんの自主性に任せる場合は、この機能を活用すると良いでしょう。
ただし、小さなお子さんや自己管理が難しい年齢の場合は、スクリーンタイムやファミリーリンクなど、強制的に制限がかかる機能を使う方が効果的です。
視聴時間制限をすると、子どもが反発します。どう対処すればいいですか?
突然制限をかけると反発するのは自然なことです。
まずはお子さんとしっかり話し合い、なぜ制限が必要なのかを丁寧に説明しましょう。
健康への影響や学習時間の確保など、お子さんのためであることを理解してもらうことが大切です。
また、最初から厳しい制限をかけるのではなく、徐々に時間を短くしていく方法や、お子さんの意見を取り入れながらルールを決める方法も効果的ですよ。
視聴時間以外の楽しい活動を一緒に見つけることで、動画への執着も和らぎます。
年齢が上がったら制限を解除すべきですか?
年齢が上がるにつれて、制限の内容は見直す必要がありますが、完全に解除するのは慎重に判断しましょう。
中学生や高校生になっても、一定のルールは必要です。
ただし、厳しい制限から徐々に自己管理を促す方向にシフトしていくことが大切です。
お子さんと定期的に話し合い、自分で視聴時間を管理できるようになるまで、緩やかな見守りを続けることをおすすめします。
まとめ:子どもの健全な成長のために、適切な視聴時間制限を
子どもの動画視聴時間を制限することは、決して楽しみを奪うことではありません。
むしろ、お子さんが健康的に成長し、バランスの取れた生活を送るために必要な、保護者の愛情ある配慮なのです。
この記事でご紹介した方法を参考に、お使いのデバイスやVODサービスに合わせて、適切な時間制限設定を行ってみてください。
iPhoneのスクリーンタイム、Androidのファミリーリンク、Google TV、各VODサービスのペアレンタルコントロールなど、さまざまなツールが用意されています。
これらを上手に活用すれば、技術的な面からお子さんの視聴環境を守ることができますよ。
しかし何よりも大切なのは、お子さんとしっかりコミュニケーションを取り、一緒にルールを作り、守る習慣をつけることです。
保護者が一方的に制限をかけるのではなく、お子さん自身が納得してルールを守れるよう、話し合いながら進めていきましょう。
年齢や成長に応じてルールを見直し、お子さんの自己管理能力を育てていくことが、長期的には最も効果的な方法です。
適切な視聴時間制限と親子の信頼関係があれば、お子さんは動画コンテンツを楽しみながらも、健やかに成長していくことができます。
今日からできることから始めて、お子さんにとって最適なデジタル環境を整えてあげてくださいね。
キーワード
おすすめ記事
-
2025.11.28
映画『ナイトクローラー』あらすじと感想を徹底解説!ジェイク・ギレンホールの狂気が光る傑作
-
2025.12.09
ネバーエンディング・ストーリーのあらすじと感想!涙なしには観られない名シーン解説
-
2025.09.18
VOD最新作配信比較!早く観られるサービスはどこ?
-
2025.09.30
VODの支払い方法完全ガイド!クレカなしでも11社徹底比較